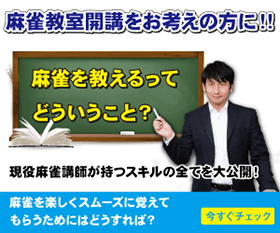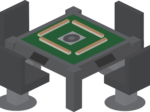麻雀新聞第199号 1992年(平成4年)2月10日
昭和23年風営法の施工 麻雀店荒らすイカサマ師
1948(昭和23)年9月1日に「風俗営業等取締法」(風営法)が施行された。この法律が制定される以前は、キャバレー、料理店、カフェー、ダンスホール、遊技場、喫茶店、旅館、公衆浴場などの取り締まりは、庁府県令に基づいて警察官が実施していた。これは、戦後の警察法改正に伴い、「風俗犯罪の予防」という見地から、警察官が取り締まる範囲は特に風俗犯罪の中で最も実質的な売春と賭博関係に限定されていたためだった。
それがこの風営法の施行によって、次の三業種が新たに風俗営業として規制されることとなった。
一、待合、料理店、カフェー、その他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二、キャバレー、ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業
三、玉突場、まあじゃん屋、その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
現在、マージャン店は第7号営業だが、この時は3号営業に規定されていた。そして、この時からマージャン営業は、許可の条件として、営業の場所、営業時間、営業所の構造、設備などの規制を各都道府県の条例によって規制されることになった。都道府県または市町村の公安委員会が営業を許可し、善良な風俗を害するおそれがある場合、また賭博行為などがあった場合は、営業取り消し、営業停止の行政処分ができた。
当時の取り締まりは非常に厳しかった。それでも、巷のマージャン店へ出入りする者は皆、賭けマージャンに勝つつもりで出かけていたから、必ず勝つ方法としてイカサマが流行した。どこのマージャン店へ行っても必ずと言っていいくらい、イカサマをする打ち手がいた。
この連中は、マージャンを職業としていて、食うためにマージャン店へ通っていたから、勝って帰らなければ、その日から食うに困ることになり、常に勝つにはイカサマ技を身に付ける以外に方法はなかった。
戦後のどさくさで人心がすさみ、物は無い時代だ。職もなく、ぶらぶらしている指先の器用な連中が、イカサママージャンを覚えて街のマージャン店荒らしをしたのだった。
こうなると、経営者も必死だ。自分の店にイカサマ師が出入りしていては、客が寄り付かなくなって店がつぶれてしまう。それを防ぐためには、その連中の入店を断っていかなければならない。イカサマの手口を見破れなければ、いいように仕事をされてしまうのだ。
最初は経営者や客もイカサマに無知だったから、自由自在にやられていた。しかし、次第に手口が分かってくると、経営者がイカサマの手口を覚え、現場を押さえて出入り禁止を言い渡し、追い返すようになった。
現場を押さえるように努力をしても、器用な者のイカサマは、一緒に打っていても分からない。指が長く細いから、ちょうどピアノを弾くようにリズミカルに牌を寄せ集めてくる。目の前でいろいろな積み込みをやられても、牌を積む動作が早いから、よほど注意して見ていないと見破ることはできなかった。
しかし、半荘で一人が大三元を二回もあがれば、これはもうイカサマ以外に考えられないから、この客は体良く断れる。上手なイカサマ師になると、このような荒技はここ一番という時でないと仕掛けない。普段は、「拾い」や「すり換え」、せいぜい「元禄積み」程度の小技で稼いでいた。
イカサマ師のことを通称「雀ゴロ」とも言った。雀ゴロは、一軒の店を断られると次の店へと渡り歩く習性があった。マージャン店の方も次第に防御策を考えるようになり、店によっては客に紹介された人だけを遊ばせるシステムを導入し、「初めてのお客お断り」の張り紙まで出すようになった。しかし、中には二人組みで仕事をする雀ゴロもいた。先に一人が店へ入り、5分か10分後に相棒が入って行く。経営者は二人が組んでいるとは知らないから、同じ卓でほかの二人の客と組ませて始めさせる。そのうちに「マスターおかしいよ。あの二人はわれわれからあがって、本人同士は決して振り込まないんだ」と、苦情が出る。
これもイカサマの一種だ。雀ゴロ同士がテンパイすると、あがり牌をサインで相棒に教える。つまり、雀ゴロ同士は決して振り込まないのだ。
そのサインは指をうまく使って送る方法が多かった。これでは一般の客は見破れず、勝てるわけもない。当時のバラ客相手の経営者は雀ゴロ締め出しのために相当の神経を使いながら経営していた。
経営者にとっては、そのほかにも注意しなくてはならないことがあった。まだほとんどのマージャン店で徹夜営業をしていた時代だ。夏場は暑いから上半身裸で打つ人もいたが、中にはイレズミをした顔付きの悪いのが、子分にヒロポン(覚醒剤)を注射させながら打っているというような店もあった。
そういう店には、真面目でおとなしい客は自然に寄り付かなくなっていく。最終的に悪質な客の扱いに失敗した店は、ヤクザがかった連中のたまり場になっていった。
また、この時期、『日本麻雀標準規程』の一部が変更され始めた。これは巷で「途中リーチ」の役が使われ出したためだった。これまでのリーチ役は、現在でいうダブル・リーチに相当するもので、最初のチー・ポン・カンの行為のない一巡目にテンパイをした時に「リーチ」をかけられるもので、それ以後のリーチ役はなかった。それがゲーム途中でも、テンパイすればリーチをかけて一翻の役が付くということで、一般にかなりはやり始めたのだ。
しかし、この途中リーチに対して、日本麻雀連盟は猛反対だった。中でも戦後の日本麻雀連盟の再建に大きく尽力した榛原繁樹氏は大反対だった。榛原氏は、「途中リーチをつぶそう」という運動を起こし、連盟の人たちに呼び掛けたが、途中リーチの役はどんどん大衆の間に広がっていった。
また、これと並行するように、大阪では「ブー麻雀ルール」が生まれていた。これは持ち点の2000点を基準点として、4人の中の1人が2000点以上プラスした場合と、2000以上マイナスした場合に、ゲーム途中でも終了して清算するというルールだ。後に東京でも大流行したが、東京麻雀組合連合会は、正統マージャンに反するものだとして大反対した。
“遊びは麻雀が中心” 青木理事長が語る大学時代
1949(昭和24)年、遊技料金は税込み半荘80円になっていたが、ほとんどの営業者は税金旋風に泣かされていた。中には税金を払えず自殺をする者も出るほどだった。同年、ドッジラインが実施され、さしものインフレも少しずつおさまり、物が出回るようになっていた。
5月には酒類の家庭配給が廃止になった。また、1947(昭和22)年7月から休業させられていた料理飲食店が再開を許可され、世の中は次第に明るさを取り戻していた。
当時の思い出を全常麻雀業組合総連合会の青木博理事長に語ってもらった。
「私がマージャンを覚えたのは、ちょうど昭和23年、大学3年の時でした。大学の寮に入っていた関係で、様々な遊びを友だちから教わりました。当時は遊びといっても、マージャンかダンスくらいなもので、ダンスも面白かったんですが、なんといってもいちばん面白かったのはマージャンですね。
ただ、終戦直後でしたから牌が手に入らず、寮の誰かが牌を借りてくると、交代で遊んだものです。まだ習いたてで、賭けることはなかったんですが、それでも寮の連中と徹夜で遊びましたね。
そのうち手の器用な友達が木の板を細く切って、万年筆で牌の絵を書き、136枚の牌を作り上げたんです。もう面白くて、なんでもいいから遊びたかったんですね。
私が大学4年生の時、家庭教師をしていた男の子のお父さんが、マージャンが強かったことを覚えています。
その人は、象牙の立派な牌を黒檀の四角いケースに4段に納めて持っていました。象牙の表面が黄色く色付いて、象牙の目があざやかに浮き出てているのを見て、思わずハッと息を飲む思いで見取れてしまいました。内心こんな牌を自分の物にしたいなという願望を持ったほどでした。
その人は、私がマージャンを好きだと言ったら、これで勉強しなさいと本を貸してくれまして、私は夢中になって読みました。その本の題名は『中国麻雀牌譜』だったと思います。内容は「中国麻雀」の格言を解説したもので、今なら当たり前のような格言ですが、そのころは全く新鮮に映り、ほとんど全部を暗記したものです。それが後年、実に役立ちました」
家庭教師をしていた時に見た象牙の牌に魅せられてマージャンのとりこになっていった青木氏自身、その後1974(昭和49)年から始まった「かきぬま王位杯争奪戦」で第1期、2期の連続王位に輝き、マージャンプロとして華々しいデビューを飾るとは夢にも思わなかっただろう。
当時、象牙牌は普通の人ではとても買えなかった。品物も無いためヤミ市での価格が一組5000円もしたのだ。1948(昭和23)年6月の巡査の初任給が2340円、公務員の初任給が2990円の時代だったことを考えればいかに高価な品物だったかが分かるだろう。
象牙牌は、かき混せる時に「カラカラ」という軽い音がして、実に優雅な印象を与える。そして、最初の象牙色といわれる独自の白色から、使っているうちに手の油が染み込んで少しずつ黄色から茶色に変色し、象牙の目がくっきりと浮き上がってくる。この目が136枚そろっているほど値段が高かった。
しかし、きれいに色が付くまでには、何年も使い込まれなければならない。したがって、一般家庭でたまに遊ぶくらいの使い方では、完全に色が付くまでに相当の年月がかかる。
それが店で使うとなると毎日数時間にわたって手脂をつけるから、数年間できれいに変色する。ただ、マージャン店では一般家庭に比べて使い方が荒っぽいから、やっと色が付いてくるころに、牌の背中の竹に傷がつき、それがガン牌になって使い物にならなくなってしまう。数年の間に背中の竹の部分はすり減って、角は丸くなり、竹の色も茶色に変色しているから、簡単に新しい牌と入れ替えることはできない。結局、その一組全部が使えなくなってしまうのだった。
こういった事情から、一般のマージャン店ではなかなか象牙牌を使うことができず、鯨骨牌か、合成樹脂を材料にした牌を使用する店が多かった。特に、合成樹脂製の牌は、価格が安い上に比較的丈夫だったので、営業用として広く使われた。しかし、丈夫とはいえ、どの種類の牌でも背中はすべて竹だったため、象牙牌と同じように、竹の色が黄色から茶色に変色する頃に傷が付いたり、竹が割れたりすると、一組ずつ新しいものとの入れ替えなければならなかった。だから、当時のマージャン店経営者は、牌を乱暴に扱う客には厳重に注意し、できるだけ傷が付かないように、静かに打牌するよう指導していた。
マージャン卓については和室の座敷で使う座卓が多かった。けやきを材料に使ったものが多く、天板にはベニヤ板に薄い緑色の布を張り付けてあった。遊ぶ時は、さらにその上に白い布を張って画鋲で止めるのが普通だった。