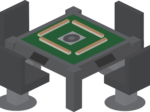1991年(平成3年)6月10日 第191号
紙牌から全自動へ
麻雀クラブ盛衰記 (4)
中国から渡来したマージャンが本家の中国以上のブームを生み、マージャンファンが増え、それに伴いマージャン経営を業とするマージャンクラブ、そしてマージャンを打つことを職業とするプロ雀士が出現するなど、中国はもちろんのこと、わが国でも予想ができなかったことだ。
現在は娯楽の多様化などが原因してマージャン店へ来るファンの数は減少しているが、まだまだ女性愛好家をふくめて熱心なファンがいる。
マージャンクラブの数はひところに比べれば少なくなったが、まだ全国で約2万6000軒、東京だけでも約5200軒の店が営業している。
マージャンのルールやマージャンクラブの形態は、昔と比べると、すっかり変わってしまった。今や中国文化というより日本固有の文化として成長し、昭和の初期にはアウトローのたまり場とされていた「雀荘」も、社交場としての「マージャンサロン」に生まれ変わってきている。
21世紀へ向かってマージャン業界はどう変わっていくのか。それを占う一つの材料として、中国伝来のマージャンのルーツを探り、日本におけるマージャンの成長過程と業界の歴史を回顧してみる。
なお、この稿をまとめるに当たり、次の資料を参考にさせていただいた。
『麻雀大百科』(双葉社)『麻雀High戦術』(後藤啓司・大泉書店)
昭和の初期は不況の渦中
麻雀人気はますます高まる
日本麻雀運盟の組織ができると同時に、ルールを全国統一すべきだという要望が強くなり、連盟としても、このまま放置すれは、せっかく組織ができたのに全国各地でまちまちのルールになる恐れがあるとして、ルール統一のための活動を開始した。
まず、マージャンを通じてつながりの深かった国民新聞社と一体になり、いろいろな団体に協力を求めて、「標準規程制定委員会」を聞くことになった。
菊地寛をはじめ浜尾四郎、松山省三などを中心に、マージャンに精通した人たちを集めた委員会は、数日間にわたって議論を闘わせた。
その結果、『昭和4年度・日本麻雀標準規程』が制定、発表され、ここに日本で初めての標準ルールが登場した。
また日本麻雀連盟は発足と同時に、国民新聞社の後援を得て第1回全国麻雀選手権大会を開催した。この大会が500人を超える参加者を得て2日間にわたって実施され、盛況のうちに終わったことにより、マージャンゲームの面白さと妙味が一般大衆に浸透し、マスコミにも大きく取り上げられるに至った。
その頃、大学生の間でもマージャン熱が高まり、多くの学生が「麻雀倶楽部」へ通うようになった。当時から学生割引料金があり、一般客が半チャン30銭のところ、学割なら20銭で遊ぶことができた。
この1929(昭和4)年、全国麻雀選手権大会と並行するように、都下大学麻雀リーグ戦が開催された。東京帝大(現・東大)を筆頭に、東京商大(現・一橋大)、慶大、早大、柘大、中央大、日本歯科大から合計40人の学生が参加し、会場の浅草『ヤマニ倶楽部』は熱気と興奮に包まれた。この大会では結局、慶大が優勝を飾った。
その年の秋にはアメリカで株価大暴落があり、世界的な大恐慌が始まった。日本もその不況の波に巻き込まれ、不況打開の道を中国の地に求めていった。そして、国民は映画とマージャンに娯楽を求めた。
日本最初の地下鉄が1927(昭和2)年、上野と浅草の間に開通し、1921(大正10)年に始まったラジオ放送が一般に広まるなど当時の東京の近代化は目覚ましかったが、その一方で失業や倒産、労働争議が相次いだ。
1930(昭和5)年に入って不況はますますひどくなり、東京や大阪などの大都市
では、「こんにちは」の代わりに「不景気ですね」があいさつになったくらいだ。男性失業者が増え、その代わりに女性が働きに出るようになり、娘たちは女工、事務員、店員などに、また家計を助けるため女給になる人妻も少なくなかった。
不景気になると賭け事がはやるといわれるように、マージャンの人気が衰えることはなく、むしろ高まっていったが、それに比例して警察の取り締まりは厳しくなった。
音楽家・福田蘭童は、その頃の様子を次のように話している。
「その頃は、現行犯でなくても捕まえられることがあった。『麻雀賭博』という罪名で捕えられ、警視庁に75日間も留置されたのが、忘れもしない昭和5年だった。『麻雀みたいな賭博を教えるなんて、もってのほかだ』というわけで、つまり、わが国の秩序良俗を乱したというのだ。1回だけでなく何度となく捕まって、その回数は他の誰よりも多いのではないか。とにかく麻雀を広めた首謀者と目されていて、直接に関わりがなくても捕えられたものだ。大阪まで引っ張っていかれたこともあるし、捕まらなくなったのは戦後になってからだ」
当時の警視庁は「麻雀亡国論」を唱えてマージャンを強硬に弾圧し、その流行を抑えようとした。しかし、流行の先端を行っている時はそんなものだが、この「麻雀賭博事件」が新聞に載ると、それまでマージャンを全く知らなかった人たちが興味を持つようになった。
なにしろ、いろいろな新聞が「一部の階級の人たちが、麻雀という支那式の賭博を楽しんでいる」などと、こと細かに記事にするものだから、「それほど面白い遊びなら、ひとつ覚えてみようか」ということになり、警視庁の意図とは逆に、一般大衆をマージャンに引き寄せる結果になってしまった。
1930(昭和5)年秋には、小田秋氏が「十三牌基準論」を発表した。それまでは中国式ルールに基づいて手牌14枚を唱える人もいて、13枚が正しいのか、14枚が正しいのかについてあいまいな解釈をしていたのが、これによって手牌13枚が確立されたといえる。
また、この頃から、『東京倶楽部』と『大阪倶楽部』による東西対抗優勝旗争奪戦の開催というように、関東と関西の交流が始まった。こうした大会は、現在の競技マージャンと同じように、1銭も賭けないで実施されたが、優勝という名誉を賭けるものだからこそ、一般ファンが競って参加したといえよう。
当時も基本ルールはアルシーアル・ルールで、振り込みでも3人払いが当たり前という解釈だった。ポンをした白、発、中などは、あがりとは別に計算する「サイド計算」という方式。振り込みの支払いは3分のーで、あがれば一人前の収入だから、振り込みが多くても取り返すのは容易というルールだ。
2000点持ちの2000点返しだから、今でいうオカは一切なし。それで、当時最高のレートは1000点10円だったが、点俸の動きが小さいから、お金の動きも大したことはない。
“銃後に娯楽は大切“
陸相に主張した平山さん
それでも、前に記したように、警察の取締まりは厳しかった。菊地寛や久米正雄、佐々木茂索、川崎備寛たちが芥川龍之介の何回忌かに「麻雀供養」をしたところ、警視庁に呼ばれて事情聴取を受けたという。
1931(昭和6)年9月18日、日本軍は満州と呼んでいた中国東北部の奉天(今の藩陽)北方に当たる柳条溝の鉄道を爆破し、それをきっかけに中国軍と武力衝突した。満州事変と呼ばれているものだ。政府は当初、局地解決を望んだが、現地軍はとめどもなく戦線を拡大し、昭和の「15年戦争」が始まった。
この頃になると、営業としての「麻雀倶楽部」も十数軒になっていたが、世の中にのさはり始めた軍部からの圧迫が激しくなり、軍国色強い世相によって、マージャンは「敵性遊技」と呼ばれるようになってしまつた。
日本で最初にマージャン営業を始めた故・平山三郎氏は当時の陸軍大臣に呼び出され「敵の蒋介石でさえ南京城外で麻雀牌を焼き捨てたのに、君たちは、この敵性国の遊技を商売にしているとはどういうことか!」と厳しく指弾された。
相手が陸軍大臣であってもひるまず、平山氏はきっぱりと主張した。
「日本はこの戦争に百年とうたっているのではないですか。日本が大国中国と戦争を行い、その百年戦争に勝ち抜くためには、銃後の国民といえども何か娯楽がなくてはならないと考えます。銃後に娯楽があってこそ、百年戦争に勝ち抜くことができるのではないでしょうか。われわれの商売である麻雀は、最初に道具を買い求めさえすれば、後は何もいらない実に便利なゲームであります」
マージャンについて熱心だったのは平山氏ばかりではない。日本麻雀連盟の榛原繁樹氏もその一人だ。求道者のようにマージャンを考え、より合理的なルールの開発と、一般の人々にマージャンを普及させることに努力していた。
当時、榛原氏は、マージャンの対局の際に記録を取ることを考え、中国語が得意だったから中国の古い文献などを調べてみたが、それらしい資料がないため、自分で記録の仕方を考案した。それが、現在使われている牌譜の原形だ。
マンズは漢数字で記し、ソウズは洋数字にカッコを付けピンズは洋数字に丸印を付けることで区別した。
現在では、マンズは「一、二、三、…」、ソウズは「1、2、3、…」、ピンズは「①、②、③、…」、東・南。西・北はそれぞれ英語表記のイニシャルで「E、S、W、N」、三元牌は「白、発、中」という表記方法を採用している。
(つづく)