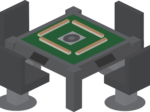1991年(平成3年)5月10日 第190号
紙牌から全自動へ
麻雀クラブ盛衰記 (3)
中国から渡来したマージャンが本家の中国以上のブームを生み、マージャンファンが増え、それに伴いマージャン経営を業とするマージャンクラブ、そしてマージャンを打つことを職業とするプロ雀士が出現するなど、中国はもちろんのこと、わが国でも予想ができなかったことだ。
現在は娯楽の多様化などが原因してマージャン店へ来るファンの数は減少しているが、まだまだ女性愛好家をふくめて熱心なファンがいる。
マージャンクラブの数はひところに比べれば少なくなったが、まだ全国で約2万6000軒、東京だけでも約5200軒の店が営業している。
マージャンのルールやマージャンクラブの形態は、昔と比べると、すっかり変わってしまった。今や中国文化というより日本固有の文化として成長し、昭和の初期にはアウトローのたまり場とされていた「雀荘」も、社交場としての「マージャンサロン」に生まれ変わってきている。
21世紀へ向かってマージャン業界はどう変わっていくのか。それを占う一つの材料として、中国伝来のマージャンのルーツを探り、日本におけるマージャンの成長過程と業界の歴史を回顧してみる。
なお、この稿をまとめるに当たり、次の資料を参考にさせていただいた。
『麻雀大百科』(双葉社)『麻雀High戦術』(後藤啓司・大泉書店)
1荘40銭は敗者が負担
トップ賞は『たばこ(ゴールデンバット)』
1926(大正一15)年になって、久米正雄が『文藝春秋』誌上に「鎌倉ルール」を発表した、これは、鎌倉在庄の文士の間でマージャンが流行して、そのグループが「鎌倉クラブ」と呼ばれたことに由来し、独自のルールだった。この頃のマージャンはもっぱら文士の遊びで、一般の人たちには無縁のものだった。
時代が大正から昭和へと移ると、マージャンはますます盛んになり、いわゆる文藝春秋派を通じて、東郷青児、飯田蝶子といった芸術家や芸能人も覚え始め、終わってから勝った者が必ず飲みに運ばれていくという習隅までできて、夢中になって遊んだという。
そして、マージャンブームは大阪へも移り、「大阪麻雀倶楽部」が開設されて次第にマージャン愛好家が増えた。
大阪府麻雀業組合連合会段審部付理事(全段番8段)だった高島実氏(故人)は当時の様子を次のように記している。
「大正の末期に好事家たちにもてはやされた麻雀が、昭和2年頃、大衆の中のインテリ層を通じて広まり、街に麻雀荘が姿をあらわし始めました。大阪ミナミの道頓堀、難波、新世界、キタの梅田、曽根崎界隈に麻雀ののれんを見受けるようになりました。当時は今と違って四人連れなどといった客はなく、一人ひとりが集まって四入になれば卓を囲むといった業態でした。一荘の料金が40銭、一流店で60銭でした。最初は各自で料金を払っていましたが、間もなく敗者負担になり、一番勝った者にトップ賞としてたばこを出す店が多くなってきました」
マージャン貸卓業を続けていた平山氏は1927(昭和2)年、正式にマージャン営業の許可を取り、屋号を『南山倶楽部』として、現在のソニービルのあたりに開店した。
これが日本で最初に営業許可を取ったマージャン店だ。この時のゲーム料金は、半チャンー卓4人で30銭。勝った人はトップ賞として7銭のタバコ(ゴールデンバット)が進呈された。当時、東京市内の店数はわずか4店だった。
この頃は、負けた者がゲーム料金を負担し、勝った者は無料で遊べるといった方式だった。現在のように千点につきいくらの賭け金を負担するというものではないから、実にのんびり遊べた古き良き時代といえる。
ほかの物価をみれば、もりそば9銭、銭湯5銭、映画館入場料30銭、公衆電話料(1通話3分以内)5銭の時代だ。
またこの年の7月には、小説家・芥川龍之介が睡眠薬自殺をしている。ブルジョアは白い手、プロレタリアは赤い手、そして自分は赤い手をしていると自己規定し、左右の政治的対立の中で苦悶する知識人のあり方を身をもって示したといわれる。
こうした時代背景の中で、いかにブームとはいえ、マージャンは一部の特殊な階級の人たちの遊びにすぎず、一般の人が自由に「倶楽部」へ出入りする習慣はまだなかった。
そのため平山三郎氏は、菊地寛、久米正雄といった文土たちを店へ招待して、マージャンルールの初歩から教えてもらったりした。今でいうマージャン教室だ。
当時はアルシーアル・ルールだから、現在のドラ入りイーハンしばりと違って、手牌の形がそろえは役がなくてもあがれるとか、振り込みの場合でも三人払いだとか、現代人には相像もできないルールだった。
それでも、この頃から「雀品」という表現でマナーが厳しく指導された。無駄なおしゃべりは極力控え、勝敗にこだわらす楽しく遊ぶことを大切にし、難しい役を競って作るのがこのゲームの醍醐味だと教えていたから、安い手で何度もあがると、「あいつは雀品がなくていかん、もう一緒にやるのはよそう」と仲間外れにされたらしい。
1927(昭和2)年10月には、空閑緑の主宰で「麻雀春秋」という機関誌が発行され、同時に第1回全関東麻雀選手権大会が開催された。大会には108人が参加したというから、まさにマージャンブームのはしりといえる。以後、この大会は1931(昭和6)年までに30回以上開かれ、ファンの底辺を広げた。
この大会に刺激されて全国各地でマージャン大会が開かれ、ブームはいやが上にも盛り上がっていった。
作家たちが特に熱中したのは、マージャンが推理力、判断力、創造力、決断力などを必要とするゲームであり、ゲームを通じて洞察した相手の性格や心理が作品を構成する上で役立ったからだろう。
マスコミも次第にマージャンブームに目を向けるようになり、新聞や雑誌に少しずつ記事が掲載されるようになった。また、マージャンの入門書や手引書が発刊され、ルールの研究も盛んになった。しかし、わが国独自のルールが確立されていなかったため、そういった書物の内容は中途半端なものや、ファンにとって物足りないものが多かった。そこで、その不満を解消しようと、ルール統一の気運が盛り上がった。
それまでは「東京麻雀クラブ規定」と「鎌倉ルール」が互いに競い合いながら、ファンを二分して採用されていたのだが、1928(昭和3)年になると、ルール協定の動きが活発化した。
当初は、二つのグループの間で相当の激論が続くのではないかと心配されたが、意外にすんなりとまとまった。
|昭和4年|
日本麻雀連盟が発足
初代総裁に菊地寛
その理由は、日本のマージャンの歴史が浅かったことと当時、マージャンに関する原典のようにみられていた『支那骨牌・麻雀』(1923年、林茂光著)をもとに両者が論議を進めたためだった。こうして、わが国初の標準ルールが制定された。
一方、大阪でも連盟結成への動きが始まっていた。その頃のことを故・高島実氏は次のように書いている。
「1928(昭和3)年、浜尾子爵や長尾克氏などの名前を聞く頃、雀荘を根城に常運がそれぞれ研究団俸を作り始めました。難波新地に富田半四郎八段を盟主として『研精会』が発足し、新町に森田・甲川六段等が『紅龍会』を、阿波座に五百田・大野六段の『青龍会』、北に一『白龍会』、『遊星会』、道頓堀に『新興会』等つぎつぎに誕生。また一方では、大阪新聞の全徳さんを中心に大阪日日の菊地七段、橋留六段、羽矢六段が指導されており、こうした同好会が関西麻雀連盟の基盤となったのです」
このように大阪独自の動きが活発化し、同好会同士で4部対抗戦や8部対抗戦が開催され、それぞれの技を競い合っていた。
そして、大阪でもルール統一の動きが起こり、大阪新聞の発案で関西ルールが制定された。それは、東京で標準ルールが発表されたすぐ後のことだった。
こうして関東と関西でそれぞれ制定されたルールは、その後、お互いに正統派を主張し合い、全国一本化は難しくなった。
そんな状況の中で、1929(昭和4)年には、愛好者の増大を背景に、マージャン歴の長い空閑緑の発案で、日本麻雀連盟の結成運動が始まった。
空閑緑を先頭に、子爵の浜尾四郎、その弟の古川緑波らが関西へ行き、関西のグループとの合併を図ったが失敗に終わった。それでも空閑緑はあきらめず、政治的手腕を発揮して全国各地の「倶楽部」やアマチュア団体をまとめ、1929(昭和4)年2月に日本麻雀運盟の発足にこぎつけた。
加盟しなかったのは「関西麻雀倶楽部」や、東京の杉浦末郎が主宰する「日本麻雀会」、高橋緑風の「本郷麻雀会」などだった。
連盟の初代総裁には文藝春秋祉社長の菊地寛が圧倒的な支持で選ばれた。当時、「文藝春秋」の読者は多かったので、この雑誌の版元の社長として、菊地寛の名前は広く知られていた。だから、新しく生まれた日本麻雀連盟を広く世の中にアピールするには最適だったわけだ。
そして、運盟の組織作りに専念してきた空閑緑は、目分が手がけていた機関誌『麻雀春秋』の内容を充実させて文藝春秋社から月刊誌として発刊することになった。
(次号へつづく)